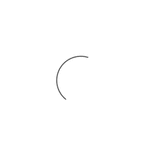
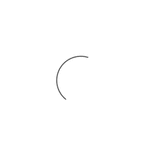

ブックレビュー
『母性』
湊かなえ 著
新潮文庫
母性というタイトルに惹かれ、購入した。
映画化されていたものは観ていない。
通勤の電車の中で読んだ。
読み始めて30ページあたりで、
正直なところ「面白くないな」と感じてしまった。
一見「綺麗な物語」に感じたからだ。
主人公の私、は神父様に懺悔する。
清らかな心を持った私が罪を乞うところから始まる。
一貫して「です」「ます」調の言葉で、母との会話もはみ出していない。
このまま最後まで、うまく収まってまとまるのか?
期待をしていただけに、少し気持ちが離れた。
そこで、一旦家の棚に“積読”して、時期を見て次のタイミングを待った。
で、今日だ。急に思い出して読んだ。
久しぶりに、ページをはじめから開く。
冒頭からの母娘のやり取りを、少しだけグッと堪えて読み進める。
随分前に読んだのに、当時読んだ記憶を元に脳内の映像が浮かんでくるよう。
いやいや、、これは。。違うぞ。
急に、この物語の面白さに気づき始める。
綺麗に描かれているようで、本質的な
私と娘の「愛のあり方」の綺麗でない、食い違いが描かれている。
娘を愛していると主張するも、その思いは娘には全く届いていない。
それどころか自分は愛されていないと思う、娘。
読書中、ずっと気になっていたことがあった。
一人娘である名前が、最後の最後あたりになってようやく明かされるのだ。
それまで「おや?」と思って何度か遡って読んだりもしたが、娘の名前は明かされていない。
p307・・・・・・
私は娘の手を握りしめ、彼女の名前を呼びました。
「清佳(さやか)!」
叫びながらふと思いました。この子の名前は清佳だったのだ、と。
・・・・・本書より引用・・・・
こんなこと、思う?
いくら姑が娘の名前を無理くり勝手に決めたからって言っても、こうはならないだろう。
「親だったら、母だったら」「フツーだったら」と枕詞をつけて、
「いやーーそうはならないだろう」って、やはり突っ込んでしまう。
でも、この物語の一番の主張はここにあるような気がしてならない。
世の「母親像」に縛られて
いい妻、いい母、でありたいと願う。
夫の家族にも使用人のような扱いを受けて、家事や畑仕事や母の介護やら。
我慢ばかりを強いられながらも、逞しく生きようと奮闘する。
こんなに振り回されている母、っている?
実は母を助けるのは、他でもない娘だ。
唯一の理解者と言ってもいい。
しかし、きっと娘自身そのことさえ気がついていないだろう。
娘を愛せない後ろめたさ、からか、
『愛を能(あた)う限り』という
フツーでは到底表現しない、言葉で
『娘を大切に育ててきました』と愛情表現する母。
ああ、なんて、おめでたくも不器用な。
刺繍のついたハンドメイドのバッグよりも、
美しい家に住まうことよりも、
母として清く生きようとすることよりも、
子どもの手が荒れていたら、
ハンドクリームをつけて、手をさすってあげ、
子どもの名前を呼ぶだけ、でいいのかもしれない。
一度は読まなくなった理由も、読み終えて最終的には納得した。
見せかけで綺麗なもの、よりも大拙なこと。
言葉や表現などは、いくらでも記憶の上書き、ができる。
いがみあっている親子関係だって、いつしか過去を修復できるはずだ。
そんな希望がある小説だった。
これが私なりの、母性、としての解釈だ。