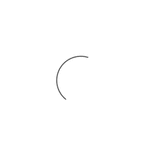
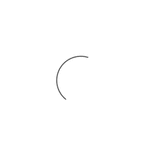

15過ぎたら、親からの
「片付けなさい」は通用しない。
子どもの声掛け、せいぜい15歳まで。
思春期を過ぎ、中学卒業。
高校に入学する子も多くいる。
成人二人を含む子供を4人育ててわかったことだが
中学生と高校生では見た目はあまり変わらないようで
高校生になると、中身がだいぶ大人になる。
中学生は義務教育と言われる様に、まだ幼い。
学習面はさることながら、
公共の場での社会性や
人との距離感の取り方や
自分の考えの確立。
高校生になると
もう半分大人と言ってもいい。
もう半分(人によってはほとんど)大人の様な15歳に子供扱いはできないのだ。
もちろん15歳から片付けを始めても遅くはない。
けれどそこには「子供扱いしない」態度で臨むことをお勧めする。
片付けにもゴールはある。
15歳までを片付けのゴールにしていただいてもいい。
年齢の話をしたが
子どもに「片付けをして欲しかったら」
まずはどんな年齢であれ、
一緒に片付けることをお勧めする。
イチから片付けられる子はいないからだ。
自分も幼少期、親から「片付けろ」と言われ、
がらんどうの半分の押し入れスペースにおもちゃを「突っ込んだ」記憶がある。
中はぐちゃぐちゃで、どうみても
子どもの私から見てもそれは「片付いた」ことにはなっていなかった。

片付けは、何をどこにどう置くか。
見た目だけの問題でもないが
押し入れに突っ込んで視界から消す、ことは決して片づけとは言わない。
親がサポートして、初めて片付けは成り立つ。
「片づけなさい」口ばかりの指示ではダメだ。
果たして、一緒に片付ける覚悟はあるだろうか。
一言で片付けると言っても、
単に「捨てる」だけではないことは、何度も記事でお伝えしてきた。
簡単には
①ものの把握(物量/状態/使用頻度など)
②要or不要の判断
③処分or使い直しor譲るなど、ものの進路を決める
これらを小さい子に教えられるだろうか?
当然難しいし、途中で飽きてしまうのが関の山。
だから一緒にすすめるのだ。
飽きたらそこで「試合終了」してもいい。
どうしても肩に力が入ってしまうと
親主導になり、子供は「やらされている感」だけが残り
「片付けはつまらないもの」と刷り込まれてしまいかねない。
そうならないためにも
子どもに主導権を。
親はあくまで子どもをサポートする。
口を出さない。手を出さない。心を出さない。
けれど目は離さない。
「高かったからもったいない」と口を出し
「これ汚いから捨てちゃえばいい」とゴミ袋に勝手に捨てる
小さかった頃の思い出だからとっておきたい「親のエゴ」も
全部、いらぬこと。

子どもが何を考え、何を選び、何を捨てるのか。
この目でしっかりと見る。
子供が困った時だけ、口も手も心も出していい。
また親が率先して「片づけたい」場合には
子どもに一言。
思春期は特に見られたくないものもあるからだ。
こんな私でも、机、バッグ、スマホの中は断じて開けない様にしている。
ここ15年くらいは、子どもたちに
「片づけなさい」を言っていない。
プリントの山ができようが、机の上が散らかっていようが、空のペットボトルを放置しようが。
気になった時に、気になった場所を、自分の判断で片づけられるようになる。
信じることも親のつとめだろう。