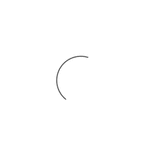
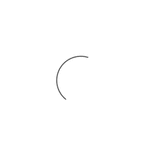
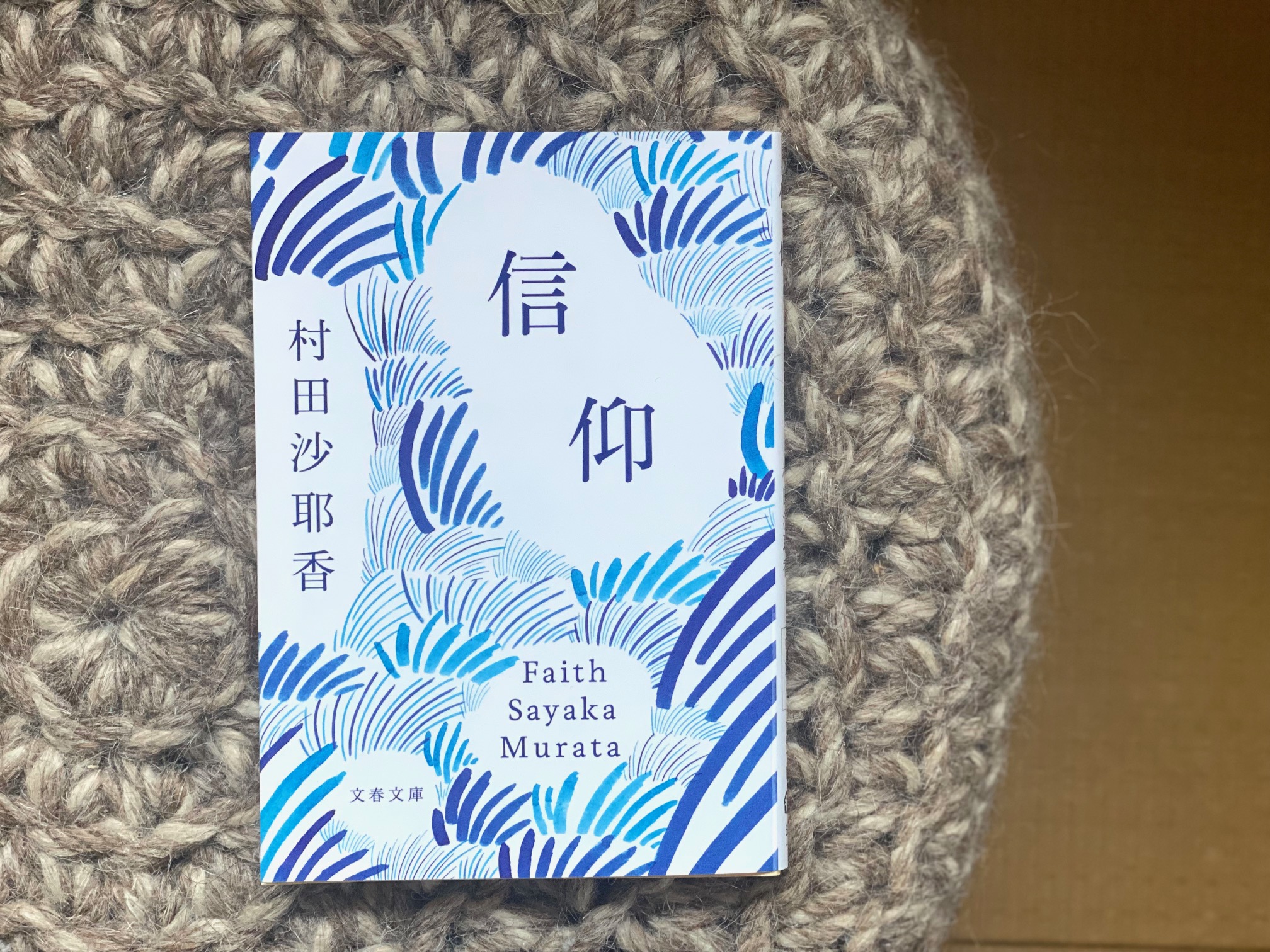
「ねぇねぇ、何か大阪弁喋ってよ」
小学一年の秋、
大阪枚方から東京三鷹に転校してきた私に
同級生が声をかけてきた。
関西から来た転校生が珍しかったのか。
それとも、一人でいる私と仲良くなろうと思ったのか。
もはや声をかけた同級生の顔も名前も覚えていない。
けれども、その言葉が40年も経った今でも引っかかっている。
当時は「何か」「喋れ」と言われて、
頭の中はフリーズし、曖昧に笑って何も言わず、やり過ごした。
小学生の頃は今でいう「生きづらい」子、だった。
友達は一人か二人だったか、当時の記憶がぽっかりと、ない。
給食はほとんど食べない。忘れ物は毎日する。
授業中もぼーっと窓の外を見ているような子で、勉強も遅れをとっていた。
親も心配で学校にも相談したようだったが、
私に対しては何か働きかけるようなことはしなかった。
唯一それが救いだった。
前置きが長くなった。
📕📕📕
村田 沙耶香 著
文藝文庫
📕📕📕
帯の文中セリフ。
「なあ、俺と、新しくカルト始めない?」につられて購入した方も多いだろう。
紛れもなく私もその一人だ。
短編の小説と随筆からなる一冊。
どの作品も「フツーでない」
これを通常運転・フツーの感覚で読んでいたら、ダメだ。
頭の中空っぽにして読むのがいいだろう。
どうしたらこんな感覚になるの?
村田沙耶香氏って、、化け物かよ。
と思いながらページをめくる。
途中、不思議な感覚にも見舞われる。
淡々と粛々と物語が過ぎていくのだ。
フツーでない世界が、逆転してフツーになったかのように。
p106・・・・・・
子供の頃、大人が「個性」という言葉を安易に使うのが大嫌いだった。
確か中学生くらいのころ、急に学校の先生が一斉に「個性」という言葉を使い始めたという記憶がある。今まで私たちを扱いやすいように、平均化しようとしていた人たちが、急になぜ?という気持ちと、その言葉を使っているときの、大人たちの気持ちの良さそうな様子がとても薄気味悪かった。全校集会では「個性を大事にしよう」と若い男の先生が大きな声で演説した。「ちょうどいい、大人が喜ぶくらいの」個性的な絵や作文が認められたり、評価されるようになった。「さあ、怖がらないで、みんなももっと個性を出しなさい!」と言わんばかりだった。そして本当に異質なもの、異常性を感じるものは、今まで通り静かに排除されていた。
・・・・本文『気持ちよさという罪』より引用・・・・・・
またその後『多様性』についても掘り下げている。
「その言葉を使う権利は自分にはない」と村田氏はいう。
言葉そのものを丁寧に扱う、ご本人の覚悟を感じる。
そして村田氏の、ある意味叫びのような
不器用な生きざまが、本書には詰め込まれている。
村田氏のように幼少期に本で救われた人もいれば
他にも芸術、映画、文化に触れ、
そして人との出会いによって変わる。
本文p184『いかり』である一人の女性と出会ったことで道が開かれる。
ようやく答え合わせができた。
やっと51年間生きてきて、小学生の頃を思い出せたのだ。
「大阪弁喋って」と言ってきた同級生の「態度」に反応していただけだった。
やはり今でもお願いされても話したくないだろうな。
大嫌いだ、こんなアプローチは。
長く蓋をしていた「フツーじゃない」ことを
さらりと話せるようになった。歳をとったから、だけではない。
これも人や本書との出会いで、自分を認めてくれる存在がいたから、だ。
人と本。
本も出会いだ。
ぜひ
あなたのとっておき、を増やして欲しい。