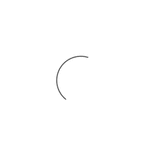
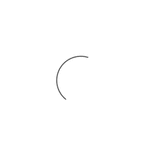

「中身がわかるようにラベリングしますか?」

片付けに伺うクライアント宅にて
整理収納の作業が終わった際に聞く。
「やらないで良いわ」
「お願いします」
二通りの答えが返ってくる。
ラベリング、
収納にラベルを貼ること。
どんな収納にラベルを貼る?
また
ラベリングすることで得られるメリットは?
片付けの現場では
一旦作った収納。によく使う。
片付けで物が移動し、定位置が変更になった場合、
慣れない置き場で「あれ?どこ行った?」を防ぎ
物の居場所を明らかにするため。

ましてや家族がいるご家庭は特に
物の場所を家族共有するために。
一旦作った収納だが
ラベリングをしても「定着しない」場合もある。
「何だかしっくりいかない」
再度見直しが必要になる。
それを見越して“きちんとラベル”を作り込まない。
慣れる場所を作るためにラベリングがある。
ご自宅にある、
引き出し、扉、箱、の中。
開けないで一発で中身を言い当てられるだろうか?
「あれ?何が入っていたんだっけ?」
中身が思い出せない。
そんな事はないだろうか。
片付けあるある、なのでご心配無く。
こんな場合にラベリングが威力を発揮する。

そのために
中身を精査し、何が入っているか明らかにする。
「お父さんの衣類」
「晩酌のための酒類」
「子供の幼稚園時代の思い出」など。
ただ貼って終わりではない。

そこに、お父さんの衣類があるから
お母さんのセールで買ったワンピースは入れらないし、
いただいた子ども服お下がりも入れられないし、
お父さんもその引き出しに衣類があると初めて分かったり。
ラベリングは「存在意義」を明らかにする。
自分を信じることは良いことだが、
それは時に「過信」になる時がある。
2でもお伝えしたが、
中身が思い出せない収納はある。
これは使用頻度が低い物に多く見られる。
扉が閉まっていても、その中にある物が酒類とわかる
なぜなら
毎日〜週1くらいで使う、使用頻度が高い物だから。

あまり触れない物は記憶から離れていく。
頻度が低いもの。
例えば、
使わないが取って置きたい。
レコード、コーヒーミル、旅行の思い出オブジェシリーズ。
引き出しや扉付き棚やバンガーズボックスに。
忘れる訳がないかも知れないが、
住所に表札があるように、収納にもラベリングを。

人が住む住所が決まってあるように
モノにも収納という帰る場所がある。
日常の慌ただしさから
自分の“立ち返る場所”を再発見することだってある。
ラベリングを貼るために
必要なもの
ラベルライター(電気店などで購入可能)

手書きシール(100均、文具店で購入可能)

荷札(100均などで購入可能)

貼る位置は
カゴ →一番メジャーでわかりやすい
棚板 →カゴに貼れない、カゴが無い場合
扉や引き出し前面→収納の中身が多いなど
ラベリングは多少の手間がかかるたため
ぜひご自身にあった方法で
必要な収納に必要なラベリングをしていただけると幸いだ。