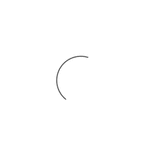
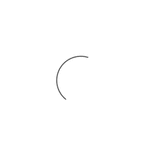

「“捨てる”を“手放す”に変えていただけますか?」
これは以前、ある機関誌の連載記事監修の際に、
内容を“捨てる”表記を訂正希望した
編集者に送った私のメールの一文だ。
“捨てる”という言葉が大嫌いだった。
昨日の『北の国から』23話レビュー記事でも触れたが
純たちのボロボロのスニーカーを母の恋人・吉野が靴屋で買い替える。
新しい靴と引き換えに、古いボロボロのスニーカーを店で捨てることになる。
それでも吉野はその時に子供達に「いいか?(古いスニーカーを持って帰るか)」と確認した。大人としてちゃんと子どもの尊厳を守った(やはりスマートな男だ)
が、純たちは雰囲気に流されるように捨てた。
最後のシーンでも警察官に吉野の行動に「事情をよく知らないから」と捨てたことに擁護している(純も大人だ)
このボロ靴、
五郎が富良野でワゴンで一番安い靴を選び「これが最高」と純たち半ば強制的に履かせた、スニーカー。
1年間、純たちの足を守り、生活を共にした。
21話では最後に、五郎が彼らのスニーカーの破けた部分を縫っているシーンがある。
うう、切ない。
物を大切に使う、当たり前でありながら、その気持ちにグッとまた涙が出る。
このシーンが20代に観た頃から30年以上もずっと心に残っている。
むしろ今の方が、その想いはより濃くなってきているだろう。
泥のついた一万円札、空知川を走る蛍も、大好きなシーンだが。
それにしてもこのシーンだけは自分にとって、別格なのだ。
当然、自身が片付けの仕事をする、ずーーーっと前のことなのだから。
因果なもんだろう。
「捨てるのは悪か?」
そう問われると違う。
私が言いたいことは
持ち主の気持ちを知らずして「捨てられる」のは不本意なのだ。
本人が「意思」を持って捨てるか。
他人が察して「勝手に」捨てるか。
同じ「捨てる」といっても
雲泥の差、大きな違いがある。
いくらどれだけ相手のことを思っていても、相手がその気になっているような素ぶりを見せようが、私は勝手に人のものは捨てたくはない。
クライアント宅で床に落ちている、明らかなゴミであろう
丸まったレシートだって、それを広げて「捨てます?」と確認する。
例外としてクライアントから丸投げされたら、こちらの判断で処分するが、
基本的に捨てない。
「捨ててスッキリ」なんて言葉は自分に対するものであって、
他人(家族であっても)に対するものではない。
なんといっても、この言葉自体、デリカシーのカケラもない。
相当めんどくさいヤツだ、と自分でも思う。
何かにつけて、“引っ掛かり”がある人間は周りをややこしくする。
冒頭の編集者だって「ああ面倒くせえ」と思っていただろう。
反論の余地もない。全くその通りなのだ。
しかし。
「捨てる神あれば拾う神あり」
これも事実。
捨てなければ、諦めなければ、手放さなければ。
いつまで経っても「成長」「新たな自分」「更新」は無し。
実際に、目の前の物を捨てて、軽やかになった経験は私だけではなかろう。
今では「捨てる」言葉も嫌いではない。
いざ
捨てるのだ。
自分の手で。自分の意思で。
もう、くすぶっている時間はない。