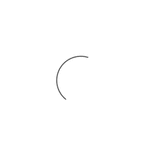
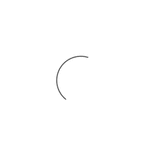

窮地に立たされたとき、人の「品」が問われる。
『恍惚の人』
有吉佐和子著
新潮文庫
敷地内の離れに済む、舅の茂造が老人性痴呆症にかかる。
主人公・嫁の昭子が甲斐甲斐しく介護する姿を描いた長編小説。
なんとこの本、昭和47年に発刊されたもの。
当時は女性は結婚後専業主婦で家にいるもの。男尊女卑の色も強く残っている。
夫の信利と共働きで生計を立て子育てをしながら、家事もこなす兼業主婦、昭子。
しかも、介護は自宅ですることが一番良い。とされる時代。
そんな中、舅が痴呆症に。
仕事をしながら、自宅介護をすることの大変さ。
さらに夫は「(実の)父は自分のことを覚えてくれていない」のを理由に何もしない。
それでも一人息子で高校生の敏は、
そんな「ボケたおじいちゃん」「忙しい母親」のフォローもしてくれる。
ここでも時代の変化を感じつつ、読み進める。
p156・・・・・・
「子供っていうより、動物だね、あれは」
「まあ、敏」
「犬だって猫だって飼い主はすぐ覚えるし忘れないんだから。自分に一番必要な相手だけは本能的に知っているんじゃないかな」
敏は滅多に茂造のことについて、親と語りあったことはなかったが、彼なりに観察をしていたらしい。
「ママが飼い主だって言うの」
「そうさ、パパを覚えてたって何もしてくれるわけじゃないからね。親だ子だって言ったって駄目なんだよ。本能というのは生きる知恵なんだから」
「でもお爺ちゃんは敏のことも覚えているのよ」
「僕も少しは役に立つ相手なんだろ」
「そうなのかしら。そういうものなのかしら」
「僕も迷惑だと思うけどさあ」
「・・・・・・・・・」
・・・・・(本文より抜粋)・・
世代間の違い、血縁関係があるなしに関わらず老人への関わり、
専業主婦とワーキングマザー、
それぞれの立場の心の機微の描き方が手に取るように伝わる。
また、当時、もしかしたら現代も、かもしれないが
老人社会問題を明らかにした作品であろう。
各家庭で親を介護する、そこには家族以外の誰にも言えない、言ってはいけないという、恥ずかしさを隠す社会であったこと。
痴呆症への理解、協力。共有。
重いテーマでありながら、
次は何が起こる?とページが進む。茂造の行動もリアルに描き驚くことばかりだ。
茂造が子供のようになる、思わず笑いが込み上げてくるシーンが多々ある。
以前は気難しく、嫁の昭子にも嫌味を言っていた茂造であったが
後半穏やかな表情に包まれる。
p333・・・・・・
「お爺ちゃん、どうしたんです」
小柄な昭子が茂造の視線を辿って見上げると、道の向こうの塀の中から大きな樹木が葉を繁らせていて、その緑の中でしとどに濡れた泰山木(たいさんぼく)の花が、目のさめるような白さで咲いていた。
雨だから、傘をさせばつい下を見て、泥にぬかるんだ道ばかり眺めて歩くものであるのに、茂造は濡れることには頓着なく、傘をかまわず上を向いて歩いて、雨の中で豪華な咲き方をしている花を認めたのだろう。昭子は、胸を衝(つ)かれていた。泰山木の花は美しかった。
・・・・(本文より抜粋)・・
今まさに、老いを感じながら生きているが
残りの人生、品のある人間になるために、どうしたらいいか。
ヒントが詰まった作品である。